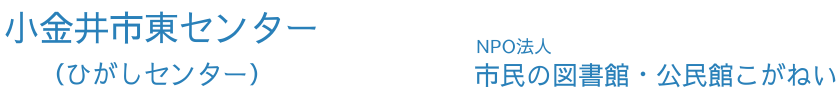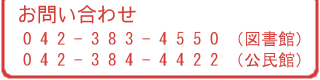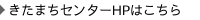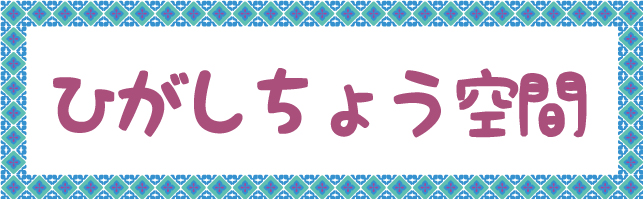想像力を高めて「その時」に備える防災実践講座 大好評実施中です(4)
想像力を高めて「その時」に備える防災実践講座では、これまでの3回で「生き残る」ことに焦点をあててきました。残る2回は、「食べる」ことを取り上げます。生き残るために重要なことは、家具の配置や避難経路を確保・確認する、普段から想像力を高めて想定外に対応するなどの「今すぐにできることを実行する」でした。また、自助・共助・公助の観点から見れば、「災害発生時から3日分程度の備蓄をしておく」ことが重要でした。「食べる」というのは、この、災害発生時からしばらくの自宅避難、地域での助け合いを想定しています。
今日のテーマは「非常食を食べる―家庭料理をご一緒に―」というもの。講師の小室満子さんが、非常時にはあらゆるものが貴重に、そして不足するのではないかと素晴らしいアイデアを提案してくださいました。すなわち、「ポリ袋で調理する方法~最小限の水・最小限の道具で いつもの食事を~」というものです。
その調理法とは?
①鍋に水を入れる。半分くらいでも可。
②ポリ袋(食品用の高密度ポリエチレン)に、1~2人分の食材・調味料を入れる。
③鍋の水の圧力を使いながら、ポリ袋の空気を抜く。
④空気が入らないように口をしっかりと閉じる。
⑤袋を鍋の水に入れ、加熱し、沸騰したら、弱火にして、火を止めたら余熱で蒸しながら火を通す。
⑥袋を開封しないまま配り、袋から出さないで、食器などにかぶせて食べる。
調理法が違うというだけで、食材は「いつもお家にあるもの」です。お米はもう袋に小分けしてありますね。小分けしたら、開封するまで味や水分を整えないので、「じっくりと揉みこんで、まんべんなく混ぜる」ことがポイントです。
.jpg)
そして、お米、おかずの袋を作ったら、袋からの漏れがないかよく確認。空気もできるだけ抜きます。そして、お鍋にお米の袋も、おかずの袋も、すべて入れます。それから火をつけて、沸騰させて、弱火にして、火をとめたら蒸らして・・・。空気をしっかり抜いておくのは、お鍋の中でできるだけプカプカ浮かないようにするためです。加熱すると蒸気が出て浮かびますので、時折お箸で返したり、浸したりします。蒸らしの段階では、「蓋を開けない」ほうがいいでしょうね。

今回は、たくさんのおかずを作ったので、開封してお皿に分けました。しかし、災害の後には、開封せずに配るほうが衛生的で、しかも食器にかぶせて食事をすればお皿を汚すこともありません。食器がなければペットボトルを切断して使う方法もあります。調理に使ったお鍋の水も汚れていません。そのまま煮沸消毒や、次の食事の用意に使えます。つまり「最小限の水を使う」ということは、「水を次のことや他の用事に残しておく」ということでもあるのですね。この方法なら、1日一人3リットル(家庭に備蓄する水の目安)を大切に利用できそうです。
市で備蓄しているアルファ米「五目ごはん」も一緒に試食しました。左から時計回りに、①かぼちゃとドライレーズンのサラダ、②地元の家庭菜園の水菜、③切干大根と人参の中華サラダ、④無洗米とミクスベジタブルのカレーピラフ、⑤(中央)無洗米のごはん、⑥非常食としてポピュラーな「アルファ米五目ごはん」、⑦大豆の水煮缶と乾燥ひじきの煮物。⑧そして大鍋料理として「各班で適当に切り分けて、大鍋に投入して、適当に味噌で味付けして、水溶き小麦粉をスプーンでいれた」、ありあわせのすいとん汁です。

すいとん汁は小さなお子さんにはいいですね。食事の時は汁物があると「ほっと安心」することができます。大鍋料理を作る際は、食材から水が出るから少なめの水で作る、出汁が出るから調味料を少なめにする、小さめに切り分けないと配るときに食材が偏ってしまう、という注意点がわかりました。各家庭から少しづつ持ち寄った材料でもできそうですね。
ポリ袋調理は、「非常時でも家庭の味を楽しめるから心が和む」、「いつもの食事を食べるっていいなと思った」、「火の通りを良くするように切り分ければいいだけ」、「下ごしらえさえしっかりとすれば、あとはお鍋が作ってくれる」、「時間もとられないし、食材や水、エネルギーも最小限で、とても合理的な方法だと思った」、「前にテレビで見たけれど臭いや加減がわからなくて。実際にやってみたら臭いもないし、調理の見当がついた」などの感想がありました。
「一人の食事の時に、たくさんのおかずが一度にできる」、「非常時だけではなくて、病気の時にもいいのではないかしら」、「時間のある時に作って、そのまま冷凍保存すれば便利に使えそう」、「子どもの運動会の前に教えてほしかった」など、暮らしの中で活かせそうな場面もたくさん出されました。

中央で立ってお話されているのが小室さん。毎日のご飯を楽しんでいらっしゃるので、お料理のアイデアがどんどん出てきて、そしてとても説得力があります。
参加した方の言葉に全員が共感しました。「忘れないうちに、もう一度自分ひとりで作ってみて、家族や自治会の人にも伝えたい!ポリ袋調理は実際にやってみないとわからない!」。
特別な非常食では、いざという時にうまくできません。いつもの料理で、いつものように。素敵なアイデアとレシピを教えてくださった講師の小室満子さん、どうもありがとうございました。次回は「常災兼備」の考え方を取り入れて、「買う→食べる→買う→食べる・・・」の備蓄サイクルに挑戦します!
発行日:2016/11/29 (令和-2年11月29日) 最終更新日:2016/11/30 (令和-2年11月30日)
アクセス・インフォメーション
住所
郵便番号 184-0011
東京小金井市東町1-39-1
東センター
交通機関
JR中央線 東小金井駅から徒歩約15分
西武多摩川線 新小金井駅から徒歩約3分
三鷹駅から「小田急バス鷹53新小金井駅行」乗車、新小金井駅下車徒歩1分
CoCoバス 中町循環(0) 新小金井駅バス停下車徒歩3分
CoCoバス 東町循環(10)新小金井駅バス停下車徒歩1分
電話・E-MAIL
| 東センター 図書館東分室 | 電話:042-383-4550 |
| 東センター 公民館東分館 | 電話:042-384-4422 E-MAIL: k020413☆k.email.ne.jp |
| NPO法人 市民の図書館・公民館こがねい | 電話:042-385-3401 FAX :042-385-3402 E-MAIL:info☆ntk-koganei.org |
E-MAILアドレスは☆を@に変更してご利用ください。
休館日・開館時間
休館日
東センターの休館日は図書館・公民館とも
毎月 第1火曜日と第3火曜日、年末年始、ほか臨時休館日(図書館)です。
開館時間
図書館は午前9時から午後7時まで
公民館は午前9時から午後10時まで
地図